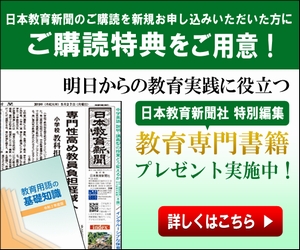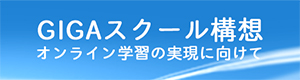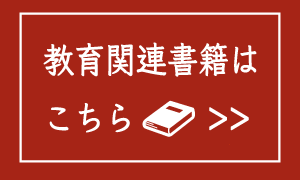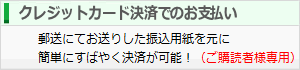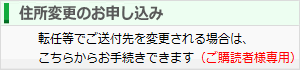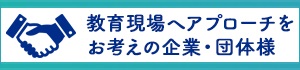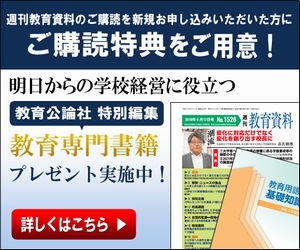脱衣時の配慮など検討 学校健診の在り方で初会合
文科省有識者会議
文科省は19日、今後の学校健康診断の実施方法について議論する有識者会議の初会合を開いた。児童・生徒の健康課題が多様化・複雑化していることや、プライバシーへの配慮の必要性などを踏まえ、意義や内容などを見直す。養護教諭の負担軽減にも触れる。座長には聖マリアンナ医科大学予防医学主任教授の高田礼子氏が就いた。
学級編制のミスマッチを解消 小1でプレクラス導入
東京・港区
東京都港区教委が本年度、区内の全ての小学校1年生に1カ月間のプレクラス(仮学級)制度を導入した。多様な児童が入学するようになる中、経験の浅い教員が担任に就くことも増えており、クラス編制のミスマッチを防ぐ狙いがある。学校現場からは「事務作業は増えるが、子どもが安心な学校生活を送れるようになる」などの声が上がっている。
女子中高生、STEM企業訪問 理系進学を後押し
民間組織
「山田進太郎D&Ⅰ財団」(東京・港区)は、女子中高生の理系進学を推進しようと企業訪問の機会などを提供する「Girls Meet STEM for School」で、学校、学年、学級単位の参加申し込み受け付けを始めた。理系分野への興味が薄い生徒の参加に期待を寄せる。皮切りとして15日には、私立校の女子生徒が都内のIT企業を訪問。会社説明や女性社員との交流を通じ、理系職への理解を深めた。
校務のICT化推進 打ち合わせはChat中心
岡山・玉野市立荘内中学校(下)
前回に続き、「生徒が主役」の学校づくりを進める岡山県玉野市立荘内中学校の取り組みを紹介する。今回は主にICTの活用と、住田義広校長から教職員への働き掛けの内容をまとめる。
0歳児・1歳児の混合クラス編制 年下の子に優しく接する姿多く
認定こども園星の子保育園(大津市) (下)
横浜市中屋敷保育園
子ども一人一人の自分らしさを大切にするとともに、保育者も「心から楽しい」と思える保育に取り組んでいる大津市の(社福)大津せんだん会 認定こども園星の子保育園〔中西淳也園長、園児86人。隣接する姉妹園の認定こども園ひだまりの家第二星の子(定員50人)と交流保育を実施〕。子どもたち同士が関わり合い、育ち合うことに向けた「0歳児と1歳児の混合クラス編制」を実施するとともに、保育者の個性を大切にした取り組みも進めている。
多様化の時代、目標定め自己実現を
教師の「個別最適・協働的な学び」とは(上)
堀田 龍也 東京学芸大学教職大学院教授
ICTを活用し、新たな授業研究と教員研修の在り方を示した一冊の書籍に今注目が集まっている。「GIGAスクールはじめて日記5 教師の学びも個別最適・協働的に!」(さくら社、写真下)だ。子どもだけでなく教師にも「個別最適・協働的な学び」が求められている。それはなぜなのか。本書の監修者である堀田龍也・東京学芸大学教職大学院教授に聞いた。上・下で紹介する。
先に結論あり 根拠を「逆向き証明」 筋道立てて考える力育む
福島大学附属中学校(小川宏校長、生徒419人)は15日、「中学校数学科授業づくりセミナー」を実施し、研究副主任の小林倫之教諭が提案授業を行った。デジタル教科書などICTの効果的な活用に加え、「逆向き証明」で筋道を立てて考える力を育む重要性にも触れた。数学科の授業づくりを共に学ぶコミュニティーを目指している同校の本セミナー。次回は秋ごろの実施を予定している。
美術通し英語学ぶカリキュラム構築 コミュ力と発信力を育む
東京・杉並区の女子美術大学付属高校・中学校(石川康子校長、生徒1050人)は、美術を通して学ぶ英語科の授業を展開している。生徒が興味を持つ美術と関連付けた教材を使い、コミュニケーション力の育成を目指す。英語と美術を融合したカリキュラムを構築した英語科の教員らは、昨年度の文科大臣優秀教職員表彰にも選ばれた。
小学生「朝の居場所」で調査 「自宅で一人に不安」就労している保護者の3割弱
こども家庭庁
小学生がいて、保護者が就労している世帯のうち、3割弱には登校前の時間帯に子どもだけが自宅で過ごす時間帯があり、不安を抱えていることが分かった。こども家庭庁が「朝の居場所」について調べた。長く、小学校では、授業前の早い時間帯から児童を受け入れる実態が珍しくなかったが、近年は、教職員の働き方を適正化しようと、受け入れ時間を遅らせる動きが出ている。朝の居場所を設けている市町村の割合は1.4%にとどまった。
「ホスト」は支援学級の児童 段ボールで小屋作り
技術教育研究会で実践報告
小学校から大学までの教員・研究者らで構成する技術教育研究会(代表委員=尾高進・工学院大学教授)が10日、「ものづくりで育つ特別なニーズをもつこどもたち」を主題とした公開研究会を開いた。小学校の特別支援学級で学ぶ児童が「ホスト」となって、段ボール製の小屋作りを通常学級の児童と楽しむといった実践報告があった。