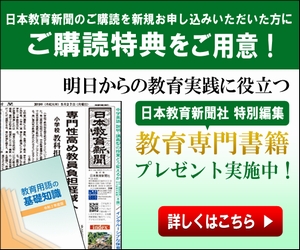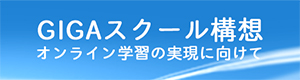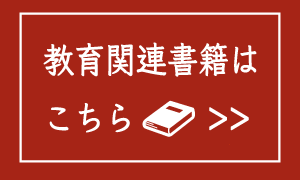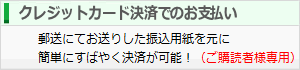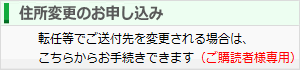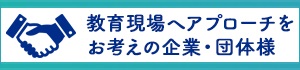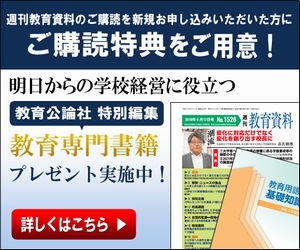給特法改正案、衆院で可決 時間外勤務の削減目標盛る
公立学校教員の処遇改善などを目的とした教員給与特別措置法(給特法)の改正案が15日、与野党の賛成多数で衆議院本会議で可決された。政府の原案に、時間外勤務の削減目標などを附則に盛り込む修正が加えられた。参議院に送られ、今国会で成立する見通し。
次期指導要領 小学校、年間875時間へ削減を 標準授業時数で提案
東京学芸大 大森教授
次期学習指導要領での標準授業時数は小学校で年間875時間程度に削減すべきだ―。14日、東京学芸大学の大森直樹教授が記者会見を開き、提案した。その上で大森教授は「減らさないと学校現場が立ち行かなくなる」と訴えた。中学校については1単位時間を45分にした上で年間945時間程度にすべきだとしている。
解説 情報モラル教育 事例基にトラブル回避考えて
学校生活に慣れ始めた5月は、SNS等を使ったトラブルが多く発生する時期。子どもたちの新しい人間関係を良好に保つため、教育現場の対策も必要となる。10代のネットトラブルに詳しいITジャーナリストの高橋暁子氏(成蹊大学客員教授)に、情報モラルを身に付けさせるための取り組みを解説してもらった。
「学校を君たちにあげる」と宣言 「生徒が主役」重視、主体性育む
「学校は特定の誰かのものではない。だから、この学校を君たちにあげる。君たちのものだから、君たちの力でより良い学校にしてほしい」―。こんな呼び掛けを入学予定の小学6年生や在校生に行い、「生徒が主役」の学校づくりを進める岡山県玉野市立荘内中学校(住田義広校長、生徒353人)。主体性を育んでいる学校として徐々に知られるようになり、地元メディアからの取材や各地の教育関係者からの視察が続いているという。同校の改革の一端について今回は生徒会活動、次回はICTの活用と教職員への働き掛けを中心に紹介する。
一人一人の今と未来の幸せを考える 自分らしさを大切に
認定こども園星の子保育園(大津市) (上)
「子どもの今と未来を幸せに」を保育理念として、子ども一人一人の今と未来の幸せについて本気で考え、日々の保育に取り組んでいる大津市の(社福)大津せんだん会 認定こども園星の子保育園(中西淳也園長、園児86人)。子ども一人一人の自分らしさを大切にするとともに、保育者も「心から楽しい」と思える保育について、2回にわたり紹介する。
ICT使った不登校支援例は 福岡・春日市教委と校長会が冊子
不登校児童・生徒は全国で34万人を超え、毎年過去最多を更新している。そのような中、福岡県春日市教委と同市立小学校長会・中学校長会は冊子「令和6年度版エデュケーションかすが ICTを活用した不登校児童生徒等への学習支援」を作成した。同冊子には19(小学校12、中学校6、市教育支援センター)の実践を収録。ICTを活用した個別指導や組織的対応に加え、学級担任やクラスの子どもたちが長期入院の児童とオンラインで交流する取り組みなどが紹介されている。
体育・保健体育 最先端技術を活用した新しい学び
AIなどの最先端技術を活用した授業に、学校現場の興味・関心も高まっている。その一例として、鈴木直樹・東京学芸大学准教授らが手掛ける体育・保健体育科の新しい学びについて紹介する。
自然保護の課題、絶滅危惧種の状況確認 小笠原諸島で合宿
桐蔭学園中等教育学校・生物部
横浜市にある桐蔭学園中等教育学校(玉田裕之校長)の生物部が、春休みに小笠原諸島で合宿を行った。絶滅危惧種が生息する自然環境の課題を学び、他校の生徒・学生や社会人とも交流した。この経験を生かし、新年度の活動にも意欲的に取り組み始めた。
「しなくてよいと言われた」など教員・母親から性差別多く 中高生に民間調査
ジェンダー意識
ガールスカウト日本連盟は4月28日、「中学生・高校生のジェンダーに関する意識調査2024」の結果を公表した。中学生の4人に1人以上、高校生の4割以上が、性別を理由に「しなくてよいと言われた」「やらされた」という経験をしていることが分かった。3割以上の中高生が、教員は男女平等に接していないと感じていることも明らかになった。
教員の「安心感」が鍵 大人は離れ、子どもの世界を
医療的ケア児の受け入れ
木内昌子さんに聞く MEPL代表(看護師)
文科省の調査によると、幼稚園・学校生活を送る上で医療的ケアが必要な子どもの数は令和5年5月時点でおよそ1万1千人。令和3年に「医療的ケア児支援法」が施行され、地域の学校で受け入れが進む一方、ガイドラインの策定は各自治体に委ねられており実態はさまざまだ。首都圏約40カ所の小・中学校等に看護師を派遣する一般社団法人MEPL(メープル)代表で看護師の木内昌子さんに、支援体制構築の要点を聞いた。
(本紙特別記者・小出弓弥)