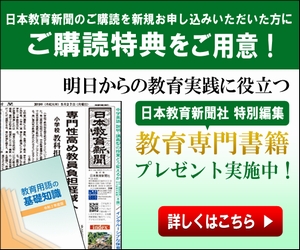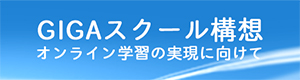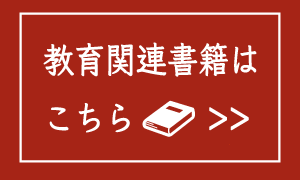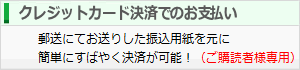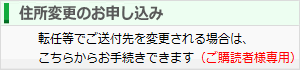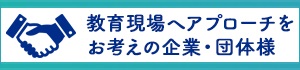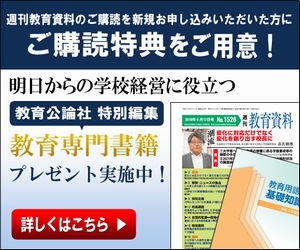デジタル教科書 紙と併用継続望む声強く
教育関係団体に聴取
中教審WG
中央教育審議会のデジタル教科書推進ワーキンググループは4月28日、デジタル教科書を正式な教科書と位置付けることとした2月の中間まとめに対する教育関係団体の意見を公表した。各団体からは、紙とデジタルの両方の特徴を生かせるよう併用を続けることを求める意見が目立った。文科省は教科や発達段階に応じたデジタル教科書導入の利点を引き続き検討し、年内に最終報告をまとめる。
放課後の居場所を豊かに 学童保育、質の確保が課題
共働き家庭の子どもを預かる放課後児童クラブ(学童保育)の利用者が増加している。一方、一部の施設では、過密な環境で長時間を過ごすことがストレスとなり、子ども同士のトラブルや職員への暴言などの問題が表面化している。子どもたちが幸せな放課後を過ごすためには何が必要か。
東京都中学校長会 定期総会・研究発表会
東京都中学校長会は4月24日、令和7年度定期総会・研究発表会を東京・東大和市で開催した。堀越勉会長の退任に伴い、佐藤敏数・武蔵野市立第二中学校校長=写真=が会長に就任した。
公平で包摂的な幼児教育・保育実現へ
東大CEDEPが公開シンポ開催
経済協力開発機構(OECD)は「OECD幼児教育・保育白書第8部 幼児教育・保育への投資による不平等の是正」を公表した。東京大学発達保育実践政策学センター(CEDEP)は4月18日、オンラインで公開シンポジウムを開催し、白書の内容について理解を深め、公平で包摂的であり、公正な学びと育ちの機会を提供する幼児教育・保育を実現するための課題や施策の在り方について考えた。
文科省などが「子どもの読書活動推進フォーラム」を開催 優秀実践校2小学校が発表
学校図書館を効果的に活用
「子ども読書の日」と定められている4月23日。文科省と(独)国立青少年教育振興機構は「子どもの読書活動推進フォーラム」を国立オリンピック記念青少年総合センター(東京都渋谷区)で開催した。全国各地で子どもの読書活動を推進している学校、園、図書館、団体(個人)の中から計262件を選び、文部科学大臣表彰を行った。子どもの読書活動への関心とその理解を深め、児童・生徒が積極的に読書活動を行う意欲を高めることがねらい。当日は優秀実践校など(16件)によるポスターセッションが行われ、積極的に質問している参加者の姿も多く見られた。
体育・保健体育科での最先端技術の活用 走り幅跳び・水泳VRで疑似体験
自らの課題見いだし、探究促す効果
鈴木 直樹・東京学芸大学准教授に聞く
メタバース(仮想空間)やAIなどの最先端技術を活用した実践事例が広がっている。今注目を集めているのは「教育×テクノロジー」の新たな学びだ。体育・保健体育科で行われている取り組みもその一つ。スポーツ庁委託事業を受け、「GIGAスクール環境下における体育授業の充実」などに取り組んできた鈴木直樹・東京学芸大学准教授。最先端技術を用いた授業の実態などについて聞いた。
能登半島地震 復興支援へプロジェクト
石川県立金沢商業高校
石川県立金沢商業高校(荒木徹校長)の総合情報ビジネス科の3年生(当時)が昨年度、「能登地震からの復興」をテーマに課題研究を行った。地元企業と連携しながら、郷土玩具「起き上がりこぼし」と香料を使った商品を開発し、売上金の一部を寄付。このプランは、日本政策金融公庫主催の「第12回高校生ビジネスプラン・グランプリ」のセミファイナリスト(ベスト20)にも選出された。
毎年、備蓄品で「防災給食」を 特別支援学校×防災
児童・生徒数の増加が続く特別支援学校。災害への備えは、ますます重要になっている。児童・生徒の特性への対応をはじめ、教職員の多さ、教室不足、学校施設の個別性・多様性といった事情がある。長野県学校防災アドバイザーを務めてきた白神晃子さん(立正大学准教授)への取材などから、今後の対策をまとめた。
京都市学校歴史博物館 戦後80年―来月21日から企画展
救護所になった小学校、集団疎開…
戦時の子ども生活 写真・日記で伝える
太平洋戦争の終結から80年を迎えることから京都市学校歴史博物館は来月21日から、「戦争と学校と子どもたち」を主題とした企画展を始める。市内の学校、子どもたちに焦点を当て、戦時下の学校生活や学区、子どもたちの生活の様子などを紹介する予定。常設展も戦争を扱っているが、企画展では、普段は公開していない資料を展示する。