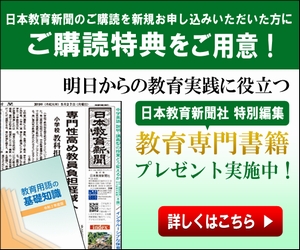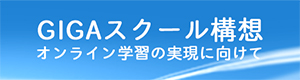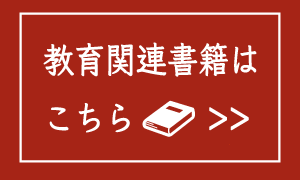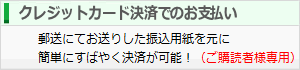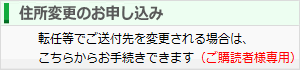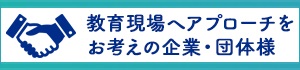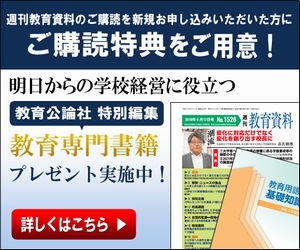理数「得意」 正答率は男女差ないが女子が下回る 全国学力調査
文科省が7月31日に公表した令和7年度全国学力・学習状況調査の結果では、各教科の男女別の成績も初めて明らかにした。算数・数学と理科で、平均正答率に大きな差は見られなかったが、質問調査で「好き」「得意」と答えた割合は女子が男子を下回った。同省では、「女子は理系が苦手」といった社会の「無意識の偏見」が影響している可能性を指摘している。
猛暑への対応迫られる学校現場 熱中症特別警戒発令で授業をオンラインに
夏の暑さが厳しさを増している。今年は6月の猛暑日となる地点が過去最多を記録した他、気温が40度を超える日も出た。部活動や校庭遊びが中止になる日が増えるなど、学校教育にも影響が及ぶ。校外の活動や外遊びを制限された子どもたちのストレスを心配する声が上がっている。
「社会の分断を防ぐ教育」で課題研究 日本教育経営学会第65回大会
日本教育経営学会第65回大会(会長=元兼正浩・九州大学大学院教授、大会準備委員会委員長=加藤崇英・茨城大学教授)がこのほど茨城大学で開催された。同学会研究推進委員会(委員長=柏木智子・立命館大学教授)の課題研究「社会の分断を防ぐ教育経営1~新たな公教育の構築に向けて~」の報告の中から、高橋望・学習院女子大学准教授の発表を紹介する。
豊かな自然環境や子どもの思い生かす 危機管理も徹底
「一人一人の子どもの人格を尊重し、受容的・応答的に関わり、興味・関心を起点とした主体的な活動を保障する」を保育の理念とし、目指す子ども像を「創造性豊かで能動的な学び手」としている静岡県富士宮市の(社福)柿ノ木会 幼保連携型認定こども園野中こども園(中村桐子園長、園児127人)。危機管理を徹底しながら、園庭の豊かな自然環境や子どもの発想を生かした、興味・関心のあることを起点に子どもが主体的に環境に関わろうとする保育に取り組み続けている。
「写す」ではなく板書から「創り出す」 常識破ろうノートの取り方
東京・新宿区立柏木小5・6年
教師の板書と、子どもたちがまとめたノートの内容が全員違う。従来とは異なる「ノートの取り方指導」を行っているのは東京都新宿区立柏木小学校(竹村郷校長、児童324人)だ。対象は高学年(5・6年)。「写す」のではなく「創り出す」という点に重点を置く。子どもたちは互いのノートをよく見合う。そのため、隠さず自信を持って「見てみて!」と言う姿が多く見られるという。
生徒が日本の将来考える参考に 全国修学旅行研究協会が第42回研究大会を開催
(公財)全国修学旅行研究協会(理事長=岩瀬正司・元全日本中学校長会会長)は7月23日、都内で第42回研究大会を開催した。大会主題は「学びの集大成を図る修学旅行」。同会が行った修学旅行実施状況調査の結果を報告した他、上原良枝・東京都港区立三田中学校校長が「シンガポール修学旅行」の実践を、杉原光信・ホテル杉長代表取締役社長が「食物アレルギー対応」の現状を紹介した。
進路希望に応じた科目を履修 配信センターを設置
広がる遠隔授業 小規模校の取り組み (下)
北海道教委は令和3年度、北海道高等学校遠隔授業配信センター(T―base)を設置し、道立高校での遠隔授業を続けている。「夢は地元でつかみとる」がコンセプトで、どの地域からでも生徒の進路希望に応じた科目履修を可能にすることが狙いだ。
通級での教科指導 期待と課題 「学びの場の連続性」高める
7月上旬に開かれた中央教育審議会教育課程企画特別部会の会合で、通級指導教室で各教科の指導をすることを可能にする案が示された。この提案を識者はどう見るか。特別支援教育に詳しい、東京学芸大学の奥住秀之教授に聞いた。
夏休み、SDGs主題に英会話 児童がALTと交流
東京・多摩市
東京都多摩市教委は7月22日、市内の小学生が外国語指導助手(ALT)とじっくり英語で会話する場を「Tama English Village」として設けた。市立小学校から募った20人の児童が、SDGs(持続可能な開発目標)に関わる世界の状況を教わった他、自分たちの学校の取り組みを紹介するなどした。写真や絵を多く利用して、英語での会話への理解を促した。