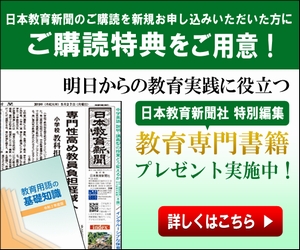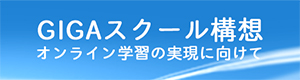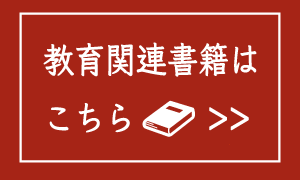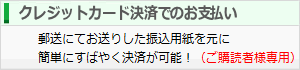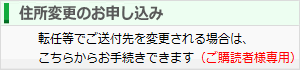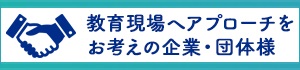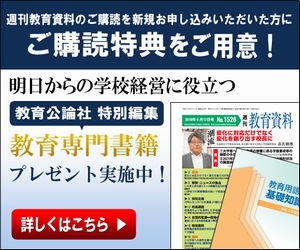高校の教育課程、柔軟に 必履修免除、科目組み替え
文科省方針
文科省は、次期学習指導要領で高校の教育課程編成の学校裁量を大幅に広げる方針を示した。各学校での教科・科目の柔軟な組み替えを認める他、生徒によって必履修科目を免除する仕組みを創設する。多様な生徒を受け入れている高校が実態に合わせて授業できるようにする。
栗山・文科省教育課程企画室長に聞く 次期学習指導要領 探究的に学ぶ姿勢重視
次期学習指導要領の検討が中央教育審議会で深まってきている。文科省の栗山和大・教育課程企画室長=写真=に改訂の要点などを聞いた。AIの時代が到来する中、子どもの興味・関心や探究的な学びを重視し、「人生をかじ取りする力」を育むことが不可欠と指摘する。
7都府県教育長に聞く 公立高校のこれから (下)
「公立高校のこれから」について、今回は全国に先行して授業料無償化が実現した大阪など3府県の教育長の考えを紹介する。
企業が「総合」を多方面で支援 校内に「サテライトオフィス」
東北地区中学校長会 研究協議会山形大会
東北地区中学校長会(会長=細谷直樹・山形市立第一中学校校長)は7月3、4の両日、研究協議会山形大会(大会実行委員会委員長=丹羽英樹・同市立第三中学校校長)を山形市内で開催した。大会主題は「豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手を育てる中学校教育」。3分科会で六つの研究・実践報告があった。
子どもも保育者も心ときめかせ遊ぶ 試し、成功して喜び、失敗して考える
岐阜市立加納幼稚園 (下)
主体性のある遊びや生活の中で「遊んで、遊んで、とことん遊び込む教育」を進め、「自分で考え行動(考動)する力の育成」をテーマに実践研究を行う岐阜市立加納幼稚園(藤井佐由美園長、園児71人)。子どもと保育者が共に創り出す「好奇心と探究心が高まる保育」は本年度も引き続き取り組まれており、7月12日に開催されたソニー幼児教育支援プログラム最優秀園実践発表会の公開保育でも、子どもと保育者が一緒に心をときめかせて遊び込む姿が見られた。
「共生の理念」運営の柱に 多様性を認め、学び合う
併設の新潟・十日町市立十日町小、ふれあいの丘支援学校
同じ校舎に併設され、共生の理念に基づく学校づくりを進めている新潟県十日町市立十日町小学校(大島一英校長、児童220人)と同市立ふれあいの丘支援学校(小林浩子校長、児童・生徒33人)。「共生の理念」を学校運営の柱とし、多様性を認め合い、学び合う教育活動として交流及び共同学習に力を入れている。同じ校舎で過ごし、交流を深めることで、子どもたちが互いを尊重しながら自然な形で関わる姿が見られる。
生徒発案で記憶に残る平和学習 「命」と「死」表現したモザイク画
子どもたちが平和の絵を描く国際的なアート・プロジェクト「キッズゲルニカ」。平和学習の一環として、その制作に取り組んだのは堺市立東百舌鳥中学校(武田真也校長、生徒759人)の3年生たちだ。修学旅行(沖縄)と合わせ、「記憶に残るような取り組みをしたい!」という思いから企画。「堺 平和のための戦争展2025」が16、17日にサンスクエア堺(堺市立勤労者総合福祉センター)で行われる。そこで生徒たちが制作した「キッズゲルニカ」も展示される予定だ。
配信機器や端末 環境整備しやすく 茨城、5月から「情報Ⅰ」で
広がる遠隔授業 小規模校の取り組み (上)
全国で高校の小規模化が進む中、遠隔授業の取り組みが広がっている。茨城県では今年5月から、県立高校2校への「情報Ⅰ」の授業配信が始まった。また、全国に先駆け遠隔授業に関する研究を続けてきた北海道は、令和3年度に授業の配信拠点を設置。小規模校で多様な教科・科目の授業を続けることを主な目的として進んでいる実践を上下で紹介する。
現場と連携、地域に根差した教員養成 高校生が教材開発など体験
上越教育大学
昨年度実施の大学入学者選抜で、教員養成系単科大学で最も競争率が高かった上越教育大学。高校生対象のプログラムなどについて、同大学大学院学校教育研究科の清水雅之教授に解説してもらった。
若者が自由に過ごす場つくる やりたいことを地域で実現
中学生・高校生世代や、もっと上の世代の若者が学校以外で過ごす場を設ける動きが各地で進んでいる。福島県郡山市ではNPOが元診療所を改装して令和5年9月にユースセンターを開設。同じ拠点で、「ひきこもり」への支援も担っている。 (本紙特別記者・渡邉康一=社会教育士)