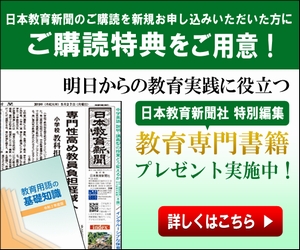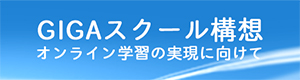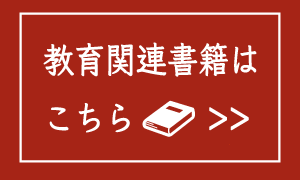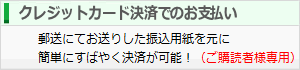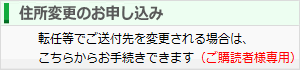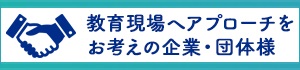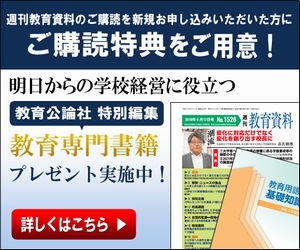中学校運動部の活動 平日1時間以内が2割
部活動の地域展開が進もうとする中、中学校の運動部のうち、平日の活動時間が1時間以内の割合は2割に上ることが笹川スポーツ財団の調査で分かった。国の指針は平日で最長2時間程度としているが、その半分以下に抑えている部も一定数あった。世帯年収によるスポーツ体験の格差が明らかになったことから、調査報告書では、財政支援により部活動を存続させることの意義を訴えた。活動の効率化は、その後押しとなる可能性がある。
不登校生徒の進学に選択肢 高校入試で受け入れ進む
昨年度、21万人を超えた不登校の中学生。高校進学時に抱える大きな悩みが調査書の内申点や出席日数だ。不登校生徒が進学しやすい環境を整えるため、高校側が入試方法を見直すなど、受け入れを強化する動きが広がっている。
AI時代の国語教育巡り意見 「指示文作りで言語力育つ」
全国教育長会議
B&G財団は13日、全国の教育長が集まり、現在の教育課題への理解を深める全国教育長会議を都内で開いた。本年度は、AIやSNSが身近な時代での国語力と人間形成を主題に据えた。講師の一人は、生成AIを使う過程で、言語力が高まるとの考えを述べた。
等身大の経験や感性が必要 日本教育会全国教育大会大阪大会(上)
公益社団法人日本教育会(鷲山恭彦会長)は1日、第50回全国教育大会大阪大会(浦山聖実行委員長)を大阪工業大学梅田キャンパス(大阪市)で開催した。大会主題は「自らの頭で考え判断し表現する力を育てる教育」。幼稚園、小・中、高校、特別支援学校、家庭・地域社会から実践を交えた六つの提言があった。
「科学する心」を共通言語に 幼保小接続を考える
ソニー教育財団 つながるまなざし研究会
「幼保小の架け橋プログラム」が全国各地で実践され、学習指導要領・幼稚園教育要領等の改訂(定)に向けた検討事項にも盛り込まれるなど、重要性が高まっている幼保小の円滑な接続。その推進に向けた動きは、民間の団体にも広がっている。(公財)ソニー教育財団は「幼保小つながるまなざし研究会」を立ち上げ、幼稚園・保育所・認定こども園等の保育者と小学校の教員が「科学する心」を共通言語に幼保小接続を考える取り組みを進めている。
支援が必要な子の学びを充実 関係機関と連携、力合わせる
仙台市立西多賀小
「未来に向かってたくましく心豊かに生き、主体的に学び続ける児童の育成」を教育目標に、特に「思いやりの心を育むこと」に力を入れている仙台市立西多賀小学校(上原広樹校長、児童461人)。発達相談支援センター(アーチル)などの関係機関と連携し、情報を共有したり、共に支援の方法を考えたりするなどして、特別な支援が必要な子どもの学びの充実を図る取り組みを進めている。
学活の学習過程を研究 安心・安全の風土醸成
岐阜・恵那市立恵那東中学校(下)
アンケートなど踏まえ議題設定
議論の流れ示し、合意形成図る成長が感じられる振り返りに
特別活動に重点を置く岐阜県恵那市立恵那東中学校(西尾新校長、生徒392人)。本年度で本研究は3年目を迎えた。生徒同士による自治的、自発的な活動の充実に向け、学級活動を要とする「学活の学習過程」に力を入れている。工夫を凝らしたのは「事前指導」「話合い」「振り返り」の三つ。学びと向き合う環境を整備し、生徒たちの学習意欲は向上。3年生は全国標準学力検査(NRT)のポイントが毎年上がり続けるという成果も出している。
課外活動のゼミ通じ主体性育む 講師の市長、医師らと議論
香川県立三本松高校
香川県立三本松高校(神前知弘校長、生徒328人)は、令和2年度から始めた生徒の主体性を育む教育活動を継続している。各分野で活躍中の社会人を招いて行う課外活動の「虎丸ゼミ」では、講師と議論する場を設けている。同校は創立125年の歴史を持つことから、多くの卒業生も後輩に経験を伝えに来ている。
SNS時代の少年非行どう防ぐ 警察と連携した自主活動紹介
民間団体がシンポ
SNS世代の少年の非行や犯罪をどう防ぐかをテーマにしたシンポジウムが11日、東京都内で開かれた。警察やサイバーセキュリティーの専門家、弁護士らが登壇し、インターネット社会で深刻化する少年非行の現状と、立ち直りを支える地域・大人の役割を語った。
少数派に寄り添う授業づくりを 教員に発想の転換求める
全国特別支援学級・通級指導教室設置学校長協会
関東甲信越地区研究協議会
全国特別支援学級・通級指導教室設置学校長協会は14日、関東甲信越地区の第40回研究協議会を山梨県で開いた。共生社会の実現やインクルーシブ教育の推進をテーマに、これからの時代に求められる子どもたちとの関わり方についての発表や、障害のある子どもの進学選択を実現するための取り組みが報告された。