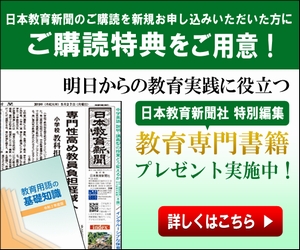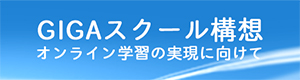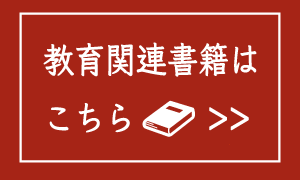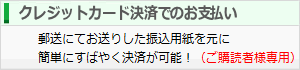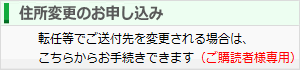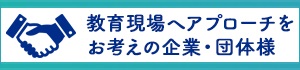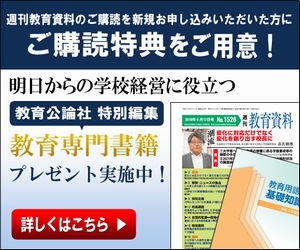地域クラブ推進へ 来月上旬にも新ガイドライン
スポーツ庁・文化庁の有識者会議は10月27日、年内にも改定する部活動ガイドラインの骨子案を大筋で了承した。指導者確保のため、骨子案には中学校以外の校種の教員が兼職兼業できる環境を整備することなどを盛り込んだ。同月30日から始めたパブリックコメントを経て、12月上旬にも新ガイドラインを策定する予定だ。
地域みらい留学 高校存続の切り札に
海外や宇宙に興味、不登校経験 生徒の多様なニーズに応え
都市部から地方の高校に進学する「地域みらい留学」が広がりを見せている。事業開始から8年目で参加校数は初年度の34校から173校に拡大。年間の利用者数も4倍超となる950人に達した。入学者の確保を目指し、地方の高校が生徒のニーズの多様化に応えていることが大きな理由だ。
「ダーク通販」に注意しよう 消費者庁 子ども向け動画教材紹介
通販サイトで余計な買い物をさせる仕組みなどについて啓発する児童・生徒向け動画教材が完成し、消費者庁が紹介している。このような仕組みは「ダークパターン」と呼ばれ、急いで買わないと売り切れてしまうとうたったり、1回の購入と見せかけて定期購入をさせたりといったものがある。製作したダークパターン対策協会では、学校教育現場などでの活用を呼び掛けている。
「県教職キャリア指標」で現状分析 全国連合小学校長会研究協議会福岡大会(下)
前回に続き全国連合小学校長会研究協議会福岡大会の内容を紹介する。今回は経営ビジョンをテーマにした分科会での高橋浩・秋田県横手市立旭小学校校長の発表と元兼正浩・九州大学大学院教授の指導・助言を扱う。
遊びの中での体験充実など検討 施設問わず、より良い育ち保障へ
幼稚園教育要領 保育所保育指針 幼保連携型認定こども園教育・保育要領 改訂・定への議論開始
幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(以下、3要領・指針)の改訂・定に向けた議論が始まった。中央教育審議会教育課程部会幼児教育ワーキンググループと、こども家庭審議会幼児期までのこどもの育ち部会保育専門委員会は10月22日、第1回会合を開催。遊びの中での直接的・具体的な体験の一層の充実に向けた指導と評価の改善・充実の在り方など、共通の検討事項を示した。今回は、諮問や論点整理などの内容を再確認するとともに、検討事項の内容を詳しく紹介する。
授業で使える指導スキル整理 「隅々まで見渡す」「曖昧な指示はしない」
A4判1枚につき10項目
「ブロックサイン10」―。A4判1枚の用紙を使い、授業中に発揮したい教師の指導技術10個をまとめたものだ。考案したのは、教師の資質・能力の向上につながる活動に取り組む鏑木良夫・NPO法人授業高度化支援センター代表(元埼玉県公立小学校校長)。特定の教科等に限らず、幅広く活用できる指導スキルが多い。教師が学ぶことで子どもたちの学びの充実にもつながる。「ブロックサイン10」を意識して授業を行うことにより、中堅・ベテランも初心に返り、自身にとって必要なスキルを磨くことができるという。
生徒主体で校則改善を図り続ける 全員にとって安心・安全な学校生活へ
茨城・守谷市立愛宕中学校
グランドデザインを生徒と共に作り上げることをはじめ、一人一人の生徒を主語とする学校運営に取り組んでいる茨城県守谷市立愛宕中学校(小林優子校長、生徒443人)。校則についても、生徒が主体となる「校則検討委員会」を立ち上げ、教職員や保護者と共に検討を重ね、改善を図り続けている。
「探究道場」での企画を発案 京都市立堀川高校など9校の生徒集う
都内でサミット
対面して意見交換 互いを高め合う
中学生に対し、生徒が探究的・発展的な学習活動に関する特別講義を「探究道場」として開いている京都市立堀川高校(船越康平校長)。全国で同様の取り組みを行う連携校に呼び掛け、10月中旬に都内で「サミット」を行った。2日間にわたり、中学生が楽しく探究ができる企画を発案する課題に挑んだ。初対面の参加者同士が交流し、最後には一つの企画を完成させた。
「体験ルーム」から入学後の支援へ 教室でコーディネーターが見守る
聖徳大フォーラム
千葉・松戸市の小学校教員ら報告
聖徳大学(千葉・松戸市)は10月25日、千葉県教委との共催で特別支援教育フォーラムを開いた。今回は、幼稚園・保育園などと小学校の連携に焦点を当てた。小学校内の一室で5歳児が小学校生活を体験する事業についての報告などがあった。この事業では、特別支援教育コーディネーターを務める小学校教員が来訪した5歳児を観察し、入学後の支援に生かしているという。
防災学び、文化財を守ろう 京都市立醍醐小 世界遺産で授業
京都・醍醐寺の敷地に面して建つ京都市立醍醐小学校(松下智洋校長、児童263人)は先月、文化財と防災について学ぶ授業を行った。創立150年を超えた同小学校よりちょうど千年長い歴史を持つ醍醐寺は世界遺産の一つ。6年生は防災関連企業が作ったボードゲーム形式の教材や消防士から火災について学んだ上で、醍醐寺の防火設備を見学するなどした。