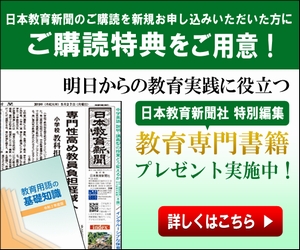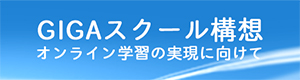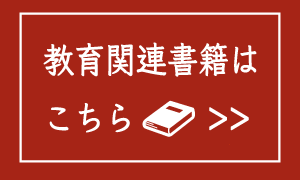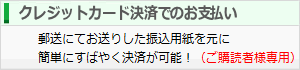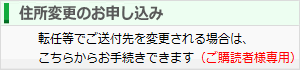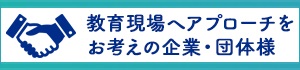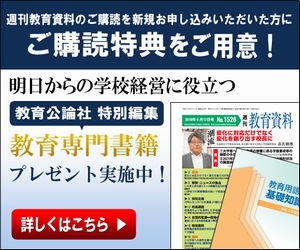教職員の休憩時間確保を 文科省 働き方改革指針改正へ
文科省は、学校の働き方改革の方向性を示す指針の改正案をまとめた。教育委員会に対し、教職員の休憩時間や休日の確保を要請。従来の学校と教師の業務の3分類を指針に位置付けた上で、学校に対する過剰な苦情や不当な要求への対応を「学校以外が担うべき業務」として整理した。新たな指針は今秋にも通知する。
戦後80年教育界は― 平和活動、SNSで発信へ 高校生ら官房長官に宣言
戦後80年を迎えた今年、高校生が国会議員に話を聞いて平和宣言をまとめる「全国高校生未来会議」が13日、議員会館で開かれた。戦争の記憶や教訓を次世代に伝えるために、高校生である自分たちにいま何ができるのか―。平和活動で学んだ内容や自らの考えをインターネットで積極的に発信していくなどとする宣言を林芳正官房長官に提出した。
高校歴史教科書 教員の8割「量多過ぎ」 内容精選、丁寧な説明望む
研究会調査
現在の学習指導要領から始まった高校の歴史科目について、担当教員の8割以上が教科書のボリュームが多過ぎると感じているとする調査結果を歴史教育の研究会がまとめた。一方で、教科書の記述自体は説明が不足していると感じている教員も4割以上いて、研究会では、扱う事項を精選し、丁寧な説明を載せるよう教科書会社や執筆者に求めている。24日に神戸市で開かれた研究大会で報告された。
「品」「個人の自由」尊ぶ流れを 全国公立学校教頭会研究大会茨城大会(上)
全国公立学校教頭会(会長=稲積賢・千葉県松戸市立第六中学校教頭)は7月31日、8月1日の両日、第67回研究大会茨城大会(実行委員長=安齊寛・水戸市立国田義務教育学校教頭)を水戸市内とオンラインによるハイブリッド方式で開催した。大会主題は「未来を切り拓く力を育む 魅力ある学校づくり」。キーワードは「自立・協働・創造」、サブテーマは「郷土を愛し 協働して未来にはばたく人財を育む 活力ある学校づくりの推進」。今回は開会行事と記念講演、次回はサブテーマを踏まえたシンポジウムの内容を紹介する。
園の存在意義や役割を語り合う 国公幼教育研究協議会東京大会から
全国国公立幼稚園・こども園長会(会長=高橋慶子・東京都目黒区立みどりがおかこども園園長)などは7月25、26の両日、東京都で第72回全国国公立幼稚園・こども園教育研究協議会東京大会を開催した。研究主題は「わくわくぐんぐん未来へ進む子どもたち―国公立幼稚園・こども園の存在意義を語ろう―」。研究発表、五つの分科会などを実施し、参加者が国公立幼稚園・こども園に期待される役割などについて語り合い、学び合った。
5年算数「プールに入る水の量は?」 「探究」意識し数学的な活動
藤田・埼玉大学教育学部附属小教諭
「プールに入る水は何リットルだろう?」―。この問い掛けで、5年算数の授業をスタートさせた藤田明人・埼玉大学教育学部附属小学校教諭。探究的な学びを意識し、「体積の学習」と「小数のかけ算」の単元を横断的に取り組んだ。授業を通じ、子どもの気付きから学んだことも多かったという。
大学が夏休みサイエンス教室
今年も全国的に猛暑が続いた夏休み。各地の大学では中学生向けの体験教室が行われた。知らないことに目を輝かせ、熱く学ぼうとしている生徒たちの姿が多く見られた。
哲学の入門書作りに挑戦 出版社で企画をプレゼン
都立小石川中等教育学校の5年生
東京都立小石川中等教育学校(小林正基校長)に通う5年生有志が、倫理の授業で作成した4コマ漫画を基に、哲学者の思想を分かりやすく伝える図書の制作を進めている。7月に代表の6人が都内の出版社で企画をプレゼン後、1時間以上にわたり出版に向けた質問を社員に投げ掛けた。夏休みには計画の実現に向け、本格始動した。
支援学校が食育の工夫報告
全国学校給食・栄養教諭等研究協議大会
茨城県で5、6日に「全国学校給食・栄養教諭等研究協議大会」が開催された。特別支援学校に関する分科会では、3校の栄養教諭が、食品の模型を使い視覚に訴える授業や、肥満生徒への個別支援などを報告。この大会は文科省や全国学校栄養士協議会などが主催した。
廃校で子どもが仕事体験 パンや生花、接客し販売
体育館を地域の「マルシェ」に
福島県白河市内で3日、3歳から小学生までの子どもたちが商品販売を体験する「西ノ森マルシェ おしごとごっこ」が開催された。会場は統合により廃校となった小学校の体育館。保護者は買い物を楽しみ、子どもは仮想通貨で報酬を得た。高校生も運営に参加し、世代を超えた交流が生まれていた。 (本紙特別記者・渡邉康一=社会教育士)