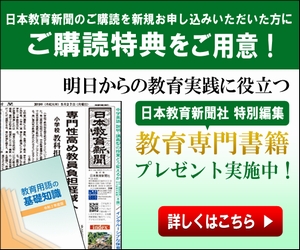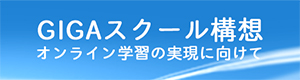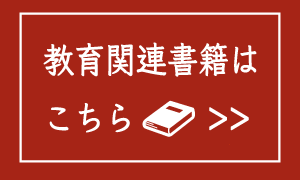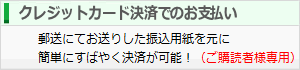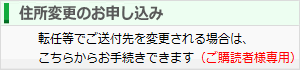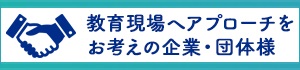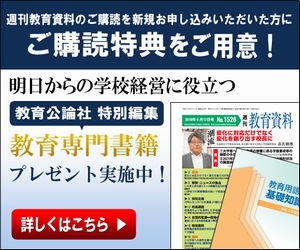算数・数学で授業が分かる子減少 全国学力調査
文科省は14日、令和7年度の全国学力・学習状況調査の結果を公表した。CBT(コンピュータ型テスト)を導入した中学校理科は統計モデルの「IRT(項目反応理論)」に基づき得点が表示され、全国平均は505点(基準点500)だった。生徒個人の結果は5段階で返却した。
「主体性尊重」と指導両立 広島・福山市教委 学力低下で方針見直し
広島県福山市教委は、教育振興基本計画の一部を改定し、子どもの主体性尊重などを掲げた「100NEN教育」を見直した。全国学力・学習状況調査の低迷などを受けた。今後は授業改善を進め、学習指導要領に示されている資質・能力の定着を目指す。
解説 夏休みの教師の学び 遊びや体験重視のワークショップを
多くの地域が夏季休業期間に入った。例年、この時期は各種の研修会がめじろ押し。複数の研究会をはしごする教員もいることだろう。今回は主に校内研修に絞って、元全国連合小学校会会長の喜名朝博・国士舘大学教授に、「学び」の充実策を投げ掛けてもらった。
学校事務職員の資質向上へ指標設定 京都市教委
学校事務職員の資質向上に関する指標を設定した京都市教委。業務への自覚などに加え、学校事務職員が自らのキャリアステージに合わせて「あるべき姿」や具体的な行動指針が示されている。年度初めに自らの目標を設定し、本指標を活用して重点的に高めたい力などを決定。学校事務支援室が中心となって作成した「キャリアアップシート」に記入し、年度の終わりに振り返りを行う。本年度から始まった新たな試みだ。
ウェルビーイング向上に向けて 国公幼総会・研究大会大分大会から
全国国公立幼稚園・こども園長会(会長=高橋慶子・東京都目黒区立みどりがおかこども園園長)は6月13、14の両日、大分県別府市で第76回総会・研究大会大分大会を開催した。研究主題は「子どもたちの明るい未来へとつながる幼児教育の創造―今、国公立幼稚園・こども園が果たすべき役割とは―」。参加者は、個人と社会全体のウェルビーイングの向上に向けた観点から、教育・保育内容や園経営の充実に向けて学び、意見を交換した。
図書館整備やNIEを推進 「ことばの力」育み、人生豊かに
広島・尾道市立御調西小
図書館の整備やNIE活動を推進することにより、児童が本や新聞に日常的に触れる環境を築き、学ぶ意欲を高めたことで、本年度「子供の読書活動優秀実践校」として文部科学大臣表彰を受けた広島県尾道市立御調西小学校(横松太江子校長、児童78人)。読書などを通して、学力の基礎となる「ことばの力」やさまざまな知識・技能、思考力、表現力などを身に付けさせ、人生を豊かに生きていけるようにすることを目指してきた。主に令和5年度から今日までの活動を紹介する。
国際交流に力を注ぐ 台湾の姉妹校と交流
岡山市東部にある岡山市立山南学園(太田圭一校長、児童・生徒387人)は、県内初の義務教育学校として令和4年4月に開校した。地域の小学校4校と中学校1校を再編した学校で、国際交流に力を入れる。昨年、同校は台湾の中学校と姉妹校協定を締結。外国人に接する機会の少ない生徒たちが、姉妹校との交流の中で英語の活用に励んでいる。
教科横断型授業と「探究」に力 多角的・複合的な視点養う
福岡県立八幡高校の普通科改革
福岡県立八幡高校(板木俊二校長、生徒823人)は、昨年度から普通科改革の一環として「文理共創科」を設置し、教科横断型の授業と探究活動に力を入れている。令和4年度に文科省から普通科改革支援事業の指定を受けた後、学際領域に関する学科として普通科を衣替えした。併設する理数科の課題研究と連動し、生徒たちによる研究発表を充実させている。
在籍校の出席認定に対応 中学生向けフリースクール、10月開校
ベネッセ
ベネッセコーポレーション(岡山市)は10月に、通学とオンラインによる中学生向けのフリースクールを開校する。8日に、入会受け付けを開始した。同日には報道機関向けの説明会を開催。入会者の学習履歴を活用し、在籍の中学校で出席認定を受けられるようサポートすることにしている。
地域との連携でキャリア意識 離職抑制を目指す
福島県立西郷支援学校(西郷村)
福島県立西郷支援学校(西郷村、鴨志田博文校長、児童・生徒126人)の高等部では、卒業後の離職率を巡る課題に対応するため、地域と連携したキャリア教育を推進している。生徒は班ごとの活動を通し、あいさつや「報連相」、協働の姿勢を学ぶ。実践的な指導を通じて、自信と職業観を育み、就労支援に力を入れている。 (本紙特別記者・渡邉康一=社会教育士)