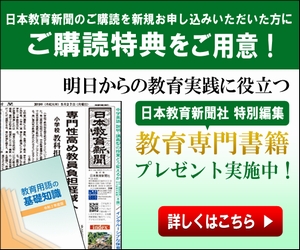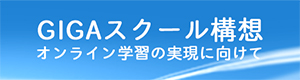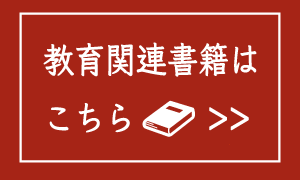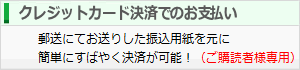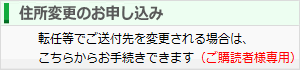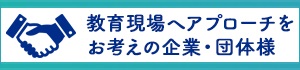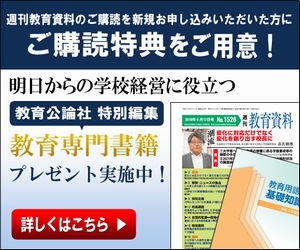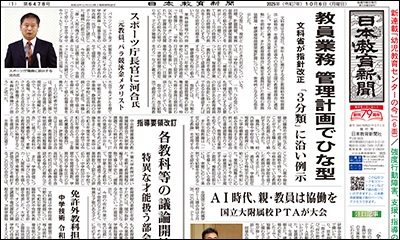
教員業務管理計画でひな型 文科省が指針改正 「3分類」に沿い例示
文科省は9月26日、来年4月に施行する改正教員給与特別措置法(給特法)を踏まえた政省令の改正を全国の教育委員会に通知した。学校の働き方改革を進めるための大臣指針に「業務の3分類」を明記した。また教育委員会に策定を義務付けた教員の業務量管理・健康確保措置実施計画について、参考例となるひな型を示した。
認定クラブに公的支援 部活動の地域展開でスポーツ庁、文化庁が検討
ガイドライン 指導者の質・生徒の安全確保策を充実
部活動の地域展開に向けてスポーツ庁と文化庁が有識者会議での議論を深めている。両庁は9月17日に、ガイドラインの改訂に向けた議論を始め、受け皿となる地域クラブを自治体が認定する制度の案を有識者会議に示した。認定を受けたクラブは、運営に関する公的支援を受けられるようにする考えだ。26日には、指導者認定制度のたたき台も示している。
私の出会った学校妖怪(下)
立田 順一 学校妖怪研究家(東京学芸大学教職大学院特命教授)
前回に続き、「学校妖怪研究家」の立田順一さん(東京学芸大学教職大学院特命教授)に、「note」に投稿した学校妖怪を紹介してもらう。
「遊び込む」ための環境構成を研究 遊具なくし材料、道具中心に
第16回幼児教育実践学会(上)
一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構(安家周一理事長)は8月19、20の両日、東京都の東京家政大学で、現場での実践を踏まえた全国研究会である第16回幼児教育実践学会を開催した。テーマは「一人ひとりの『こどもがまんなか』をまもる質の高い幼児教育を―社会全体でつむぎ未来へつなぐために―」。開会式、基調講演、園内研修のメイキング、口頭発表、ポスター発表を実施した。今回から2回にわたり、「遊び込む」に向けた環境構成や預かり保育の現状と課題など全国から30の研究・実践事例の発表があった口頭発表の内容を紹介する。
全員挙手で「話合い」促進 「自分ごと」とする意識培う
東京・練馬区立下石神井小の授業改革(上)
授業改革に乗り出し、子どもの主体性や教師の同僚性を大きく向上させた公立小学校がある。子どもの表現力(特に「伝える力」)に課題があった点に着目し、「関わり合い」に力を入れて授業実践に取り組む東京都練馬区立下石神井小学校(永井美奈子校長、児童783人)だ。「話合い」を授業改善の軸に据え、助走期間を含めて本年度で3年目を迎えた。子ども一人一人が自分の考えを持ち、どのような意見でも受け入れる学級風土が醸成されているのも特色だ。同校の取り組みを上・下で紹介する。
「読むこと」指導の基本から手ほどき 若手教員の悩みに応える
奈良県国語教育研究協議会(会長=米田猛・富山大学名誉教授)は「『読むこと』指導における教材研究と言語活動」(B5判、116ページ、写真)を刊行した。「理論編」に加え、「実践編」には五つの事例(小学校2・中学校3)を収録。各事例に学ぶべき視点などを示した「考察」を盛り込んだのは今回が初めてだ。授業力向上が期待できる一冊。「読むこと」指導に同じ問題意識を持つ国語科教員に向け、米田会長は「まず冊子を読んで実践し、自らの授業改善に役立ててほしい」と話す。
全国公立学校事務長会研究協議会・総会から 働き方改革の先進事例発表
全国公立学校事務長会(会長=小杉聖子・東京都立第一商業高校経営企画室長)は8月7、8の両日、国立オリンピック記念青少年総合センターで、第49回研究協議会・総会を開催した。研究協議では、参加者同士で対話する時間を設けた後に、各都道府県で公立学校の事務長などを務める代表者が学校事務における働き方改革の先進事例を発表。DX化を進める中で、データ管理の効率化を図ることが必要と指摘した。
「強度行動障害」支援・指導のポイントは
中西 郁・十文字学園女子大学特任教授に聞く
障害者福祉の分野で対応が進んでいる「強度行動障害」。学齢期では福祉と教育が連携して支援に当たることが求められているが、特別支援学校の現場でも認知や理解はまだまだ進んでいない現状だ。特別支援教育に詳しい、十文字学園女子大学の中西郁・特任教授に学校現場での支援・指導のポイントを聞いた。
女子中高生ら理工系の仕事体験 大学・企業が各地で講座
研究者、技術者と交流楽しむ
政府事業
「理工系のお仕事体感しよう」というテーマで、多くの大学や企業が7、8月を中心に、各地で講座を開いた。理工系の仕事や将来像に触れられる政府の事業の一環。主な対象の女子中高生だけでなく、小学生や男子高校生も参加した。理工系の内容を学ぶプログラムの他、研究者や技術者との交流を楽しんだ。