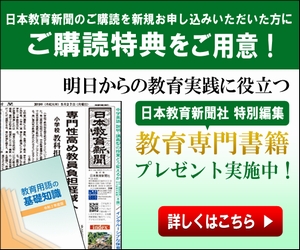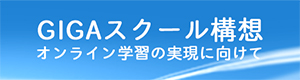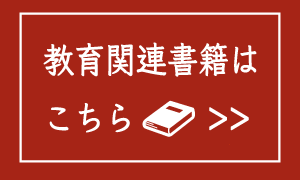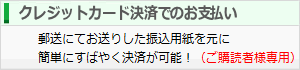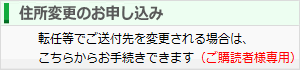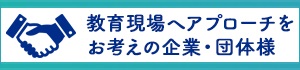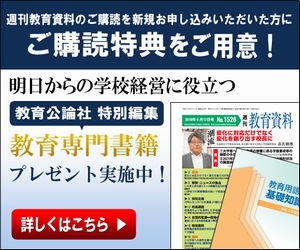社会人の教職参入を検討 「民間団体も教員養成を」中教審で報告
中央教育審議会の教員養成部会は17日、多様な専門性などを持つ社会人の教職参入を促す制度について議論した。文科省から教員資格認定試験の実施方式の変更や、企業に在籍しながら教員として勤務する人の任用形態を見直すことが提起された。また、委員からは教員養成を大学だけでなく民間団体も担えるようにすべきとの提案もあった。
高校生の就職活動 近年の変化は
求人票電子化サービスを運営、普及 前澤 隆一郎さん
企業情報、端末で探せる環境に
高校生の就職活動が本格化する時期となった。近年は、企業から紙媒体で届く求人票を電子化し、生徒が自分の情報端末で検索し、応募先を絞り込む仕組みが遅ればせながら急速に普及しつつある。就職活動電子化を支える企業を経営する前澤隆一郎さんに、高校生の就職活動の現状と今後の見通しについて話を聞いた。
7都府県教育長に聞く 公立高校のこれから (上)
政府内で検討が進む「高校無償化」。実現した場合、中学校卒業後の進学先として私立高校がより選ばれやすくなるとの見方がある。一方、公立高校には、私立には担いにくい役割を果たし続けることが求められる。高校数が多い7都府県の教育長に、公立高校の将来像などを尋ねた。
「子どもが主人公」の実践紹介 小学校長会連絡協議会
関東甲信越地区小学校長会連絡協議会 研究協議会新潟大会
関東甲信越地区小学校長会連絡協議会(会長=田沢憲・山梨県北杜市立明野小学校校長)は6月19、20の両日、研究協議会新潟大会(実行委員長=藤本高雄・新潟県上越市立大手町小学校校長)を新潟市で開催した。大会主題は「自ら未来を拓き ともに生きる豊かな社会を創る 日本人の育成を目指す小学校教育の推進」。12分科会20分散会で40の研究・実践報告があり、グループで協議を深めた。
好奇心と探究心が高まる保育 チョウ飼育、一生を観察
岐阜市立加納幼稚園(上)
岐阜市立幼稚園2園では「探究心と創造力を育む幼児教育」を推進し、主体性のある遊びや生活の中で「遊んで、遊んで、とことん遊び込む教育」を進めている。現在は「自分で考え行動(考動)する力の育成」を研究テーマとしており、市立加納幼稚園(藤井佐由美園長、園児71人)も、このテーマで実践研究に取り組んでいる。子どもと保育者が共に創り出す「好奇心と探究心が高まる保育」は昨年度、ソニー幼児教育支援プログラムの最優秀園を受賞した。2回にわたり、同園の保育を紹介する。
地場野菜使うメニュー考え、販売 企業へプレゼン、何度も試食
「僕たちの考えたサラダとカレーです。ぜひ食べてみてください!」。東京都国分寺市立第七小学校(丸山智史校長、児童540人)の6年生たちの声が店内に響く。場所はJR国分寺駅のそばにある商業施設(国分寺マルイ)。6月25日から1週間、地域の人たちに向けて販売活動を実施した。子どもたちは約半年を費やし、地場野菜などを使ったサラダメニューとレトルトカレーを開発。同校の6年生が総合的な学習の時間で取り組んできた「こくベジ メニュー企画・販売プロジェクト」について紹介する。
週4回、朝に3分間の運動 肥満傾向、体力の二極化を解消へ
福島県では、東日本大震災と東京電力福島第一原発事故発生以降、児童・生徒の肥満や運動不足が指摘されている。そこで、福島市立平野中学校(佐藤裕子校長、生徒220人)は、福島県立医科大学保健科学部の楠本泰士准教授が作ったプログラムの下、保健体育とは別に週4日間、授業開始前に運動の時間を確保し、生徒の心や体の健やかな成長に効果を上げている。
(本紙特別記者・渡邉康一=社会教育士)
専門知識・技能を実社会で役立てる 企業などの困り事をものづくりで解決へ
広島県立広島工業高校
県西部の工業高校の拠点校であり、128年の歴史と伝統のある広島県立広島工業高校(河野幸浩校長、生徒692人)。機械科、電気科、建築科、土木科、化学工学科の5学科があり、3年間の系統性を持たせた未来創造学習「KenPro」(工業探究プログラム)を核に、身に付けた専門的な知識・技能を、ものづくりなどを通して実社会で役立てる活動を展開している。河野校長に、昨年度まで勤務していた県東部の拠点校、県立福山工業高校での取り組みを交えながら、今後の広島工業高校の構想を聞いた。
全体的な課題把握し建設的な提言を 障害種別校長会と緊密に連携
緒方 直彦・全国特別支援学校長会会長(東京都立あきる野学園統括校長)
新会長に聞く
6月26、27の両日に開催した全国特別支援学校長会(全特長)は令和7年度研究大会。冒頭に実施した総会で、新会長に緒方直彦・東京都立あきる野学園統括校長が就任した。緒方新会長に就任の抱負や特別支援教育の現状と課題、全特長の果たす役割、次期学習指導要領に向けて訴えたいことなどについて話を聞いた。
居場所づくり・学習支援で公民連携 川崎市「こどもサポート」事業
川崎市こども未来局は「子ども・若者等支援事業」として、不登校や引きこもりなど、さまざまな課題や困難を抱える子どもたちを支援している。その一環で、子どもの居場所づくりや学習支援を行う拠点「こどもサポート」を2カ所に開設。市の教育支援センターとは別に、児童福祉の視点による民間の力を生かした新しい取り組みだ。