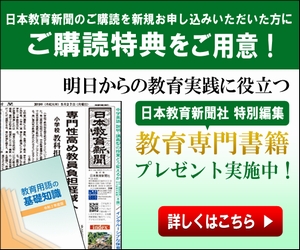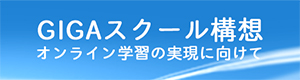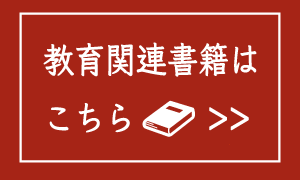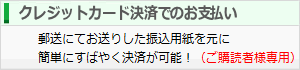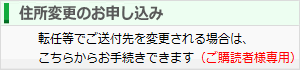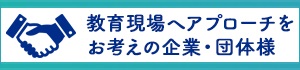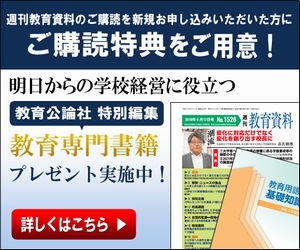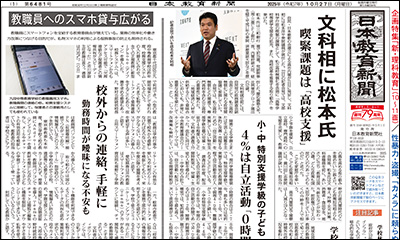
文科相に松本氏 喫緊課題は「高校支援」
自民・日本維新の会連立による高市内閣が21日に発足し、文科相には松本洋平衆院議員が就任した。22日の記者会見では、文部科学行政の喫緊の課題として、私立高校無償化を念頭に「高等学校等就学支援金の拡充、また、高校改革を推進する取り組み」を挙げた。
性暴力・盗撮 防犯カメラに頼らぬ対策は
トイレ前や廊下天井設置進むが…
有識者会議「選択肢の一つ」
教員による性暴力や盗撮の事案が相次いでいることを受けて、学校内に防犯カメラの設置を求める声が上がっている。性暴力の再発を防ぐために設置している公立中学校を取材すると、防犯カメラのみに依存せず、校内体制を整えることの重要性も浮かんだ。
全国連合小学校長会研究協議会福岡大会 (上)
全国連合小学校長会(会長=松原修・東京都武蔵野市立第二小学校校長)は16、17の両日、第77回研究協議会福岡大会(大会実行委員長=松本剛・福岡県古賀市立古賀東小学校校長)を福岡市内で開催した。大会主題は「自ら未来を拓き ともに生きる豊かな社会を創る日本人の育成を目指す小学校教育の推進」。13分科会で26の研究・実践報告があった。上下2回で紹介する。
主体的な遊びを育む園庭へ 素材の導入・実践・可能性考える
国際校庭園庭連合日本支部 研究実践セミナー(2)から
本年度「子どもの主体的な遊びを育む園庭環境づくりとルースパーツ(素材)の導入・実践・可能性を考える」をテーマに、3回の園庭研究実践セミナーを開催する国際校庭園庭連合日本支部(代表=仙田考・田園調布学園大学准教授)。その2回目として4日、豊かな里山環境のある東京都八王子市の(学)東京内野学園 東京ゆりかご幼稚園(内野彰裕園長、園児250人)の園庭・園舎を見学するとともに、同園の子どもたちの園庭での外遊びと環境の在り方、特に園庭環境づくりとルースパーツ(素材)の導入・実践について学んだ。
「授業の構想」に力 個の成長目指して
富山市立堀川小学校 (下)
「さまざまな対象と豊かに関わりながら、自らをみつめ、願う『生き方』を求めて力強く歩む」―。こうした子どもの姿を掲げ、「個」の成長に力を入れる富山市立堀川小学校(石田和義校長、児童552人)。特色ある教育活動の中で、本年度は「授業の構想」に重点を置く。その取り組みを支える教員研修と併せて紹介する。
ICTは学びの日常的道具 一人一人を一層よく見よう
第20回小中一貫教育全国サミットin呉 (下)
今後の在り方を展望
小中一貫教育全国連絡協議会は10月2、3の両日、広島県呉市で第20回小中一貫教育全国サミット(大会実行委員会会長=寺本有伸・広島県呉市教育長)を開催した。テーマは「過去 現在 そしてこれから―小中一貫教育の新たな意義を問う」。今回は呉信用金庫ホールで行われた2日目の全体会について紹介する。
活動の方向性や質在り方が定まらぬ「探究」 多様な実践、2文字でひとくくり
寄稿 小林 真也 新潟県立新津高校教諭
現行学習指導要領で導入された高校の総合的な探究の時間については、今もなお多様な議論がある。「よりよく課題を発見し解決していくための資質・能力を育成する」という目標が示されているものの、活動の方向性や質は学校間で大きな差があるのが実情だ。特定の組織に丸投げする、大学の「総合型選抜」を意識して課題設定する―といった動きもある。そこで今回は、各所で「探究」の実践や今後の在り方を発信している小林真也・新潟県立新津高校教諭に、一教諭の視点で提案を寄せてもらった。
人権擁護委員や保護司招き授業 学校と関係機関との連携の重要性を学ぶ
高知大が教職志望学生向け集中講義
宮田特別記者がリポート
学校と関係諸機関との連携の在り方や役割について考えを深めてもらおうと、元高知市立中学校校長で高知大学非常勤講師の宮田龍さんはこのほど、同大で教職を目指す学生を対象に、人権擁護委員や保護司らを招いた授業を行った。宮田さんに本紙特別記者の立場で、当日の様子を紹介してもらう。
「学校林はインフラ、地域支える」 国交省職員らに学ぶ
樹木や岩石など自然を生かして社会基盤を整備する「グリーンインフラ」に関する授業が今秋、全市立小・中学校がユネスコスクールとして活動している東京都多摩市の小学校で行われた。このうち、地域住民らの力で学校林を維持している市立豊ヶ丘小学校(佐藤真澄校長)では、国交省職員と都市環境工学の専門家を講師に、6年生がグリーンインフラについて学び、学校林でその知識を踏まえた活動に臨んだ。