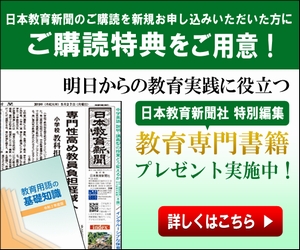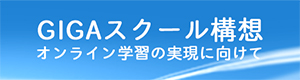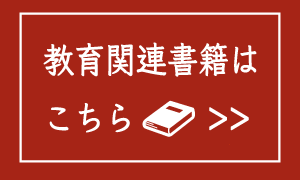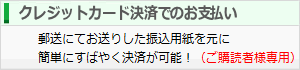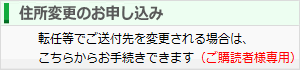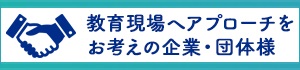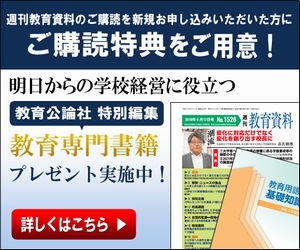教委への障害者就労 法定雇用率に届かず
都道府県・政令指定都市教育委員会のうち、障害者雇用率を達成しているのは28教委にとどまることが、文科省の調査で分かった。令和元年の前回調査時よりも実雇用率は上昇傾向ではあるものの、全国の合計では法定割合には届かなかった。調査を踏まえ同省は6月、通知を出し、障害のある教職員の活躍の促進に向けた環境整備などを求めた。
保護者・住民からのハラスメントで「弁護士対応」望む声多く
都教委が全教職員に調査
東京都教委は、保護者や地域からのハラスメント防止策の検討のために実施した教職員調査の確定値を公表した。児童・生徒指導や、いじめ・不登校への対応をきっかけとするものが多かった。対策としては、弁護士による対応や、電話の録音機・防犯カメラの設置を求める声が多く上がった。
競技や手話の体験学習 デフリンピック機運醸成
東京都などは11月中旬に開幕する「東京2025デフリンピック」の機運醸成に向けた体験学習の提供と、子どもの競技観戦・体験活動事業を進めている。6月18日に行ったメディア対象の説明会では、東京体育館で行う開閉会式を含め各競技の観戦を全て無料とすることを発表した。
強み生かし「チーム学校」推進 米国の姉妹校など多彩に交流
関東甲信越地区中学校長会研究協議会千葉大会(上)
関東甲信越地区中学校長会(会長=牛越雅紀・長野県諏訪市立上諏訪中学校校長)は6月12、13の両日、第77回研究協議会千葉大会(大会実行委員長=神子純一・千葉県館山市立館山中学校校長)を千葉市内で開催した。全体協議会では、松本聡・千葉県いすみ市立国吉中学校校長が全体協議題「新たな時代を切り拓き、よりよい社会を形成していく人間を育てる中学校教育」を踏まえて、勤務校や県内各地の特色ある取り組みを発信した他、9分科会で18の研究・実践報告が行われた。今回は全体協議会、次回は分科会での発表内容を紹介する。
遊びや生活通し探究を深める 豊かな感性、創造性育む
幼保連携型認定こども園 めずらこども園 (上)
「いつも生き生きとして新鮮で美しく驚きと感激にみちあふれた世界を子どもたちへ」を理念として、子どもたちの最善の利益を考え、真面目に面白がって熱中する時間をつくっている大分県宇佐市の(社福)芽豆羅の里 幼保連携型認定こども園めずらこども園(宗像文世園長、園児90人)。「科学する心を育てる」を中心に据え、子どもたちが遊びや生活を通して探究を深めることで豊かな感性と創造性を育んでいる。こうした探究が乳児期からつながっていく実践は、昨年度のソニー幼児教育支援プログラム優秀園審査委員特別賞を受賞した。2回にわたり、その実践を紹介する。
身の回りの疑問を題材に 筑波大主催「科学の芽」賞(下)
筑波大学が毎年実施している朝永振一郎記念「科学の芽」賞(科学コンクール)。今回は学校として活用している事例と、小学生時代に「科学の芽」賞を受賞した児童の「その後」を追った。本年度の応募は8月18日からスタートする。
「挑戦心」育む社会科実践 学習者主体の授業づくり
「よりよい社会の実現目指す姿」目標に
埼玉大学教育学部附属中学校
「令和の日本型学校教育」の実現に向け、学習者主体の授業づくりに力を入れている埼玉大学教育学部附属中学校(関口睦校長、生徒440人)。「挑戦心」をキーワードに、その意味を「探究や学びを持続させるエネルギー」と捉えて共通理解を図っている。教師たちが大切にしている軸は「手放す」こと。生徒たちに自らの学びに責任を負わせることがねらいだ。教師も粘り強く待ち続けなければならないこともあるという。今回は同校社会科の実践研究について紹介する。
生成AIで教育はどう変わる 英文添削、早く正確に 評価基準も提案
近年、急速なスピードで進化を続ける生成AI。教育現場の利用について、文科省は校務や学習場面での積極的な導入を促していく考えだ。学校の生成AI利用の最前線を追った。
専門高校校長会 総会・研究協議会から(上)
各専門学科高校の校長会の総会・研究協議会が5月に実施された。会長のあいさつに続き、各会が示した活動計画や研究協議会の内容などを、上・下で紹介する。今回は農業・工業・水産の3団体。
「伝わる文章」プロに教わる 東京理科大学、教員志望学生に4回の講座
東京理科大学が5月から6月にかけて、教員志望の学生を対象にした文章力向上講座「記者トレ」を開いた。教員の仕事は、家庭へのお便りや通知表の所見欄など、文章を書く機会が多い。最近の学校現場では生成AIの使用が広まっている。そこで講座は「生成AIを活用して『伝わる』文章を書く」をテーマに開講した。
県版アートカードで鑑賞眼培う 作品理解深め、地域文化に関心
栃木・佐野市立西中の生徒
感想・気付きを「5・7・5」に
図工や美術の授業で作品の「鑑賞」の教材となるアートカード。栃木県佐野市立西中学校では6月20日、開発中の栃木県版アートカードを使って「かるたの読み札」を作る授業を行った。生徒は作品理解と地域文化への関心を高めた様子だった。(本紙特別記者・渡邉康一=社会教育士)