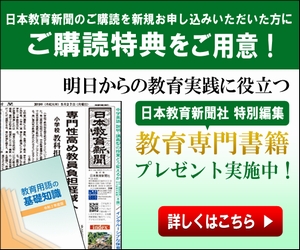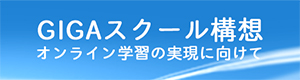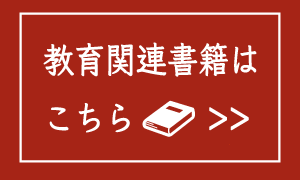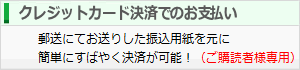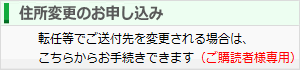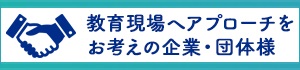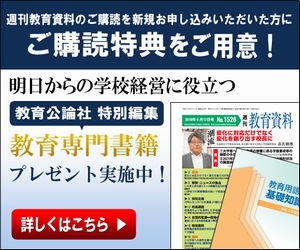学校裁量拡大、生かせるか 次期学習指導要領の枠組み 多様なニーズに対応
中央教育審議会の教育課程企画特別部会は19日、次期学習指導要領の枠組みについてまとめた論点整理を了承した。児童・生徒の多様な実態に応じた教育活動を可能にするために、授業時数の運用や科目の設定などで学校裁量を拡大することが柱。各学校には、これまで以上に計画的な教育課程編成が問われることになる。月内から各教科等の改訂について作業部会で議論を始める。
子の主体性育成と教師の指導性 「二項対立ではない」
一斉授業をベースにして
溝上 慎一・桐蔭横浜大学教授
学習指導要領の改訂に向けた議論が進んでいる。中央教育審議会の教育課程企画特別部会で委員を務める溝上慎一・桐蔭横浜大学教授(桐蔭学園理事長)は、主体的な学びと教師の指導性は二項対立ではないとして、一斉授業をベースにした「主体的・対話的で深い学び」の徹底を訴えている。8月下旬、詳しく話を聞いた。
私の出会った学校妖怪(上)
立田 順一 学校妖怪研究家(東京学芸大学教職大学院特命教授)
元横浜市立小学校校長で、「学校妖怪研究家」の立田順一さん(東京学芸大学教職大学院特命教授)は4月から、投稿サイトの「note」に、「妖怪大百科・学校編」を掲載している。9月22日現在、紹介された「学校妖怪」は60以上。各所から問い合わせがあり、妖怪が生まれた背景や職場で出会ったときの対処法について講演している。上下2回で妖怪の一部をまとめてもらった。
口唇口蓋裂の子ども 園生活での課題と求められる対応
松本 学・共愛学園前橋国際大学教授に聞く
生まれつき唇や口蓋が割れている先天性疾患である口唇口蓋裂。適切な時期に適切な治療を受ければ、通常の社会生活を送ることができる。しかし、成長に伴い見た目の問題が生じることもあり、適切なケアや対応が求められる。どの園にも対象児が在籍する可能性がある中、口唇口蓋裂の子どものケアを専門とする松本学・共愛学園前橋国際大学教授に、口唇口蓋裂の子どもが園生活を送る上での課題と求められる対応などについて聞いた。
教科等横断、官民連携で実践充実 「自分ごと」とする意識培う
札幌市小中学校環境教育研が始動
本年度、新たに発足した札幌市小中学校環境教育研究会(会長=斉藤健一・札幌市立資生館小学校教頭)の取り組みに注目が集まっている。同研究会は教科等横断的な活動を行い、官民連携で環境教育を推進。世界に誇れる環境都市を目指し、2008(平成20)年に「環境首都・札幌」を宣言した同市。本研究会も「子どもたちが環境問題を『自分ごと』で捉え、主体的に取り組む授業実践」を発信していく方針だ。
興味引き出す教材、学び方の工夫紹介 修学旅行と関連付けた平方根の学習
数学教育協議会が千葉で第72回全国研究大会
全ての子どもたちが楽しく算数・数学を学べるような授業を研究してきて74年目を迎えた数学教育協議会(数教協)は今夏、千葉県内で第72回研究大会を実施した。「子どもとつくろう数学の世界」を主題に、校種ごとに教育関係者対象の講座を行った。中学校関連では、平方根の学習と修学旅行を連携させた取り組みなどについて報告があった。
探究活動通じ競技経験を社会へ発信 本年度から新コース 背景に大学入試の多様化
三重高校 アスリートクラスの取り組み
本年度、三重県の高校総体で総合優勝を果たすなどスポーツにも力を入れる三重高校(神崎公宏校長、生徒1272人、松阪市)では、探究活動で地域貢献を目指すアスリートクラスを設置。生徒は科学的にスポーツを学ぶなどしている。
教育の「質」担保が重要 通級の基礎定数化見据え適切な学び検討して
4・27通知 「共に学ぶ」促進が目的
田中裕一・神戸女子大学教授に聞く
文科省が令和4年4月27日、「特別支援学級在籍の児童・生徒は原則、週の半分以上は特別支援学級で授業を受ける」ことを求めた通知は、インクルーシブ教育に逆行するといった批判も根強い。通知について識者はどう見ているのか。神戸女子大学の田中裕一教授(元文科省特別支援教育調査官)に話を聞いた。
防災教育で交流深める ICT活用がつないだ縁
福島・新地町と大阪・豊中市の中学校
東日本大震災で大きな被害に遭った福島県新地町。復興の過程で学校でのICT活用に力を入れてきたことが縁となり、大阪府豊中市と防災教育を巡る交流が深まっている。本年度は、同市の中学生が修学旅行で新地町を訪問。遠く距離が離れた2校の生徒が一緒になって災害について理解を増進させた。折に触れて災害について学ぶ新地町の子どもにとっても、「発信」を通して、より深い学びにつながった模様だ。 (本紙特別記者・渡邉康一=社会教育士)