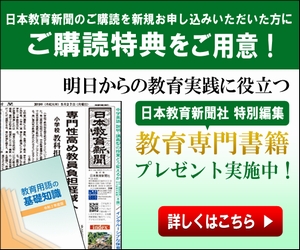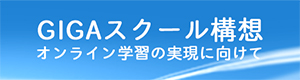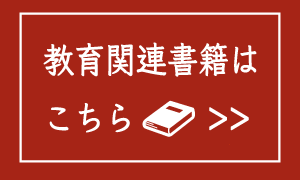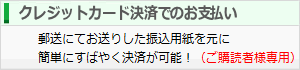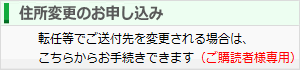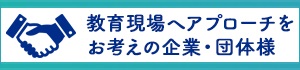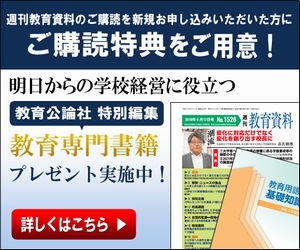学力型年内入試 首都圏私大で拡大 実施ルールは形骸化
来年度大学入学者の選抜で、学力試験を課す総合型や推薦型の入試(年内入試)が首都圏の私立大学を中心に拡大していることが教育産業大手の調べで分かった。来年度入試の実施要項では、小論文や面接を組み合わせることを条件に、2月1日より前の学力試験を認めていた。ただ、学力試験以外は評価しない大学があるなど、事実上ルールが形骸化している実態が浮かんだ。
保護者からのハラスメント対策 面談1回30分、必ず録音 都教委が指針案
専門家チーム派遣も
保護者らによる過剰な要求や暴言などのハラスメントを防ぐため、東京都教委が学校向けの対応ガイドラインの骨子案をまとめた。面談時間に上限を設け、繰り返し面談を求められる場合には弁護士に対応を委ねることもできるとした。関係がこじれて長期化する場合には、弁護士らでつくる専門家チームを学校に派遣する案も盛り込んだ。区市町村教委とも共有し、小・中学校でも参考にできるようにする。
解説 自由進度学習と読解力 教科書を活用した一斉授業も
個別最適な学びに向けて、自由進度学習の実践が各地で行われている。国立情報学研究所の新井紀子教授は、読解力向上の観点から教科書を活用しない自由進度学習への懸念を示す。詳しく話を聞いた。
豪雨災害、教訓を次の世代へ 全日本中学校長会研究協議会香川大会(下)
前回に続き、10月に開かれた全日本中学校長会研究協議会香川大会の内容を紹介する。今回は分科会での研究・実践報告を扱う。
地域・自然との関わり通じ みんながつながる
「学び合い、育ち合う、地域のコミュニティの場。幼児も保育者も保護者も園に関わる全ての人がつながり、成長する幼稚園」を目指す幼稚園像の一つとして掲げる、東京都江東区立つばめ幼稚園(神谷美和子園長、園児32人)。園の強みである「地域との深いつながり」と「豊かな自然環境」を生かし、地域・自然との関わりを通して、子どもを真ん中に「みんながつながる」ことに向けた実践などの研究に取り組んだ。
教師の2スキル軸に授業改善 働き方改革と両立、負担減る
リアクションとフィードバック 机間指導
旧井泉小学校、旧三田ヶ谷小学校、旧村君小学校が再編され、旧井泉小学校の校舎を利用し、本年度4月に開校した埼玉県羽生市立羽生東小学校(細村一彦校長、児童401人)。県教委指定の研究委嘱も引き継ぎ、学力向上に向けた授業改善を行っている。その取り組みを炭火に例え、じわじわと燃え続ける持続可能な研究であるという点も特色の一つだ。教師の働き方改革との両立も図っている。その具体的な取り組みとは―。
特別活動に力、温かく活気ある集団に 7段階の学級成長モデル示す
岐阜・恵那市立恵那東中学校(上)
学級経営の充実に向け、岐阜県恵那市立恵那東中学校(西尾新校長、生徒392人)は特別活動に力を入れている。学級活動を要とし、重点に置くのが「話合い活動」だ。年間を七つのステージで区切り、学校全体で共有を図った「学級成長モデル」を構築したところが大きな特色の一つ。学級活動や学校行事などで取り組む「話合い活動」の工夫に加え、学級や自らの成長に関する生徒の振り返りの充実も図った。さまざまな手だてを講じ、生徒たちの主体的な行動と発言が増加。同校は12月4日、研究発表会を行い、これまでの成果を披露する。
普通科存続に向けた取り組みなど発表 全普高 高松で総会・研究協議会(下)
全国普通科高等学校長会の第75回総会・研究協議会が10月16、17の両日に高松市で実施され、全国から526人の校長・教育関係者らが参集した。研究協議会では、大学入試に関する調査報告や普通科存続に向けた取り組みの紹介があった。前回に続き、発表内容などを紹介する。
トゥレット症の子学校でどう支えるか シンポで中学生が思いを語る
発声と動作にチック
自分の意思と関係なく何度も奇声を発してしまったり、顔をしかめてしまったりする「トゥレット症候群」。発声のチックと動作のチックの両方が1年以上続いている状態を指す病気で、症状は人によってさまざまだ。病気への社会的な認知度は低く、日々の生活の中で周りからじろじろ見られたり、からかわれたりする人も多い。学校では、教員や周囲の子どもの理解と支えが重要になる。
市議が支援学級で主権者教育 「校則」主題に 社会参画意識、将来担う子に培う
東京・あきる野市の中学校
東京都あきる野市議会(臼井建議長)は6日、同市立東中学校(齋藤弘圭校長)の特別支援学級で、校則を主題とした出張授業に臨んだ。3年生が対象で3~4年後には有権者となることを見据え、民主政治の基礎を知ってもらう機会とした。知的障害学級で学ぶ9人の生徒は3人ずつの班に分かれ、各班には議員が2人ずつ付いてファシリテーター役を務めた。